
いかなごのくぎ煮とは、新子に砂糖や醤油、生姜などを加えて煮詰めた家庭料理のことで神戸の郷土料理の一つとしてよく知られています💡
ちなみに新子とはコノシロの幼魚のことで、出世魚(成長の過程によって名前が違う魚)のためコノシロの幼魚でも5㎝位の小さなものを新子と言います(‘ω’)ノ
他は、
・10㎝位のものをコハダ
・13㎝位がナカズミ
・15㎝以上でコノシロ
と呼ぶのだそう。
いかなごのくぎ煮は、一風変わったネーミングですがそれは何に由来しているのでしょうか❓
今回は、
・いかなごのくぎ煮の由来
・賞味期限と保存方法、カロリー
などについてご紹介したいと思います。
いかなごのくぎ煮の由来

いかなごのくぎ煮と聞くといかなご×釘のようなイメージがありますが、ネーミングの由来には様々な説があります💡
いかなごを調理して出来上がったものが、
・全体的に見るとなんとなく古く錆びた釘に似ているから名付けられたという説
・実際に釘を入れて煮ていた(!)という説
などあります。
釘を入れて煮るなんて想像しがたいですが、名前が名前なので色々と想像してしまうのかもしれませんね…
本当のところは漁師たちのまかない料理として、鍋に沢山の新子を入れて煮る姿がまるで釘を煎っているように見えたそうで、釘煎りが釘煮となって現在のくぎ煮になったという説が有力です(‘ω’)ノ
確かに新子の折れ曲がった姿は、遠目から見ると曲がった釘のように見えなくもないですからね‼
煮詰めると色合い的にも、こげ茶のような黒っぽいような少し錆びた釘のような感じにも似ていますから確かにという感じ。
漁師のまかないが一般的に愛されるように
元手がかからず佃煮にすることで保存食として長い期間食べることが出来たので、もともとは漁師たちのまかない料理だったのですがそれが一般の人にも愛されるようになって普及していったようです。
ご飯に良く合うので、おかずがない時でもそれさえあればご飯が美味しく食べられますからね。
大体毎年2月から3月頃にかけての間収穫されるようになるので、いかなごのくぎ煮が出回る頃は春の訪れを意味していて神戸の春の風物詩と言われているんですね✨
佃煮なので、水分量が少なくその分砂糖が多めなので長期間食べることが出来ますがそれでも一応賞味期限はあります。
風味が失われないように、期限を目安にしながら早めに食べきるようにしたいですね‼
次のページでは、賞味期限の目安と保存方法についてご紹介します。

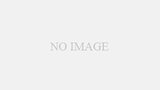
コメント