
日本には色々な記念日、イベントの日、〇〇の日と言われる日がありますがその一つに「とんちの日」があります💡
とんちの日は、毎年1月9日と決まっています(´ω`)
とんちの日って何の日なの?何で1月9日なの?と一瞬考えてしまう人も居ると思いますが、日付を見れば鋭い人はすぐにピンと来るでしょう。
今回は、とんちはどんな日なのか、なぜ1月9日に制定されたのかなどご紹介します。
1月9日は一休さんにちなんで名づけられた日
とんちと言えば有名な一休さん。
一休さんの1・9の語呂合わせで、毎年1月9日はとんちの日に制定されました。一体どこの誰が決めたのやら…という感じですが公式な記念日となっています✨
一般社団法人「日本記念日協会」では、一年間の様々な記念日が掲載されているのですがとんちの日もばっちり掲載されているのです(‘ω’)ノ
また、1月9日はとんちの日でもあるのですが実はとんち以外の記念日でもあります。
1月10日の初恵比須のお祭りである十日戎(とおかえびす)の前日ということで、「宵戎」に当たります。
十日戎には縁起ものである福笹が売られ、商売繁盛を祈願し購入して飾るものですよね。
>>>福笹の飾り方は方角に気を付ける?処分する時はどうすべき?
あとは、横綱として圧倒的な強さを誇る谷風が感染症で亡くなったのもこの日。
その為1月9日は風邪の日としても知られます。正月明けは1年でもっとも寒い時期になりますし実際に体調を崩す人も多い為風邪の日として定着したのかもしれません。
とんちの日はクイズを楽しむ日
日本人はなぞなぞ、クイズが好きな人が多いと言われています。
でも、普段自らクイズ本を読んだりクイズ番組など見なければ日常で考えたり推理することって意外と少ないのかもしれません。
考えて、推理して、予測して…と頭を使うのも楽しいものですよね🎵
1日くらいクイズをめいっぱい楽しむ日があっても良いじゃないか、ということでクイズを楽しむ日になったのかもしれませんね。
ここで2つほど一休さんに関連したとんち話をご紹介します(*‘ω‘ *)
一休さんのとんち話は有名で、沢山ありますが「水あめの話」「ろうそくの話」のご紹介です。
水あめの話
ある時、和尚さんが村人から水あめのお菓子をもらいました。
食べたそうな一休さんに、和尚さんはこう言いました。「この水あめは大人が食べると良いが、子供が食べると体に毒じゃ。子供のお前は決して食べてはいかん。」と。
そう言われた一休さんは、「わかりました。決して食べません。」と素直にうなずくと和尚さん「それは良かった。」と安心して出かけます。
しかし、一休さんは水あめがただのお菓子であることを知っています。
美味しい水あめを独り占めするなんてずるいと思った一休さんは、仲間の小僧たちと和尚さんの水あめを全部食べてしまいます。
こんなことして和尚さんに怒られないものか…小僧たちは心配し始めました。
でも、一休さんは平気な顔をしています。
和尚さんが帰る頃、和尚さんが大事に使っている茶碗を壊す一休さん。そして、皆で泣き真似をしてこう言いました。
「和尚さんの大事なお茶碗を壊してしまいました。そのお詫びに毒である水あめをなめて報いを受けようと思いましたが全て食べても効き目がありません。」
そう言われた和尚さんはしてやられたと思い、以降お菓子は分けることにしたとか。
ろうそくの話
とある晩、和尚さんは一休さんにあることを頼みます。
「一休や、本堂の火を消すのを忘れてしもうた。仏様に失礼になるから消してきてくれんかのう。」と。
「はい、和尚さん。」
言われた通りに本堂に行った一休さんですが、まだ一休さんの背丈ではろうそくの火まで手が届きません。そこで、勢いよくフーっと息で吹き消しました。
戻ってきた一休さんに和尚さんは尋ねます。
「おい一休や、どうやってろうそくの火を消したんじゃ?」と。すると、一休さんは「はい、息で吹き消しました。」と答えます。
それを聞いた和尚さんは、「この馬鹿者!仏様に息を吹きかけるなんてなんと無礼な!」と怒ります。一休さんは、「すみません。」と肩を落としてしまいます。
そして次の日、和尚さんがお経を読むと一休さんがお尻を向けて座っています。
それを見た和尚さんは、昨日叱ったものだからスネているのかと思いながらも一休さんに「一休や。仏様にお尻を向けるなんて無礼ではないか。」と注意します。
しかし一休さんは「仏様にお経をあげたら息がかかるので失礼じゃないですか」と。
確かにそうなのじゃが…
これまた一休にしてやられたなぁ、と返答に困ってしまった和尚さんなのでした。
ーーー
たまにとんち話も聞くと面白いものですよね。
一休さんのとんち話は可愛らしいものが多いので、子供の時に読んだものも改めて読み返してみるとまた違った楽しさがあるかもしれませんね。

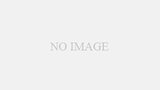
コメント