どんな語源・類語がある?

なぜ舌鼓というようになったのかというと、その語源は日本の伝統的な楽器の一つである「鼓」から来ているのだそう💡
鼓は、バチを使って打つことで音を出す楽器(‘ω’)ノ
日常的によく見られるものではないかもしれませんが、お雛様の人形が持っていたりする肩に乗せるタイプの楽器ですね。
日本人は、昔は美味しいものを食べると舌を使って上あごを鳴らすことでその美味しさを表現したり意思表示していたと言われています。
それが、「コンッ」というような音でもあり「ポンッ」とも聞こえる音だったので鼓の音に似ていることから舌鼓と言われるようになったようですよ。
舌つづみの類語には、美味しいものを食べた時に使う場合は「美食を満喫する」「美味しさを堪能する」などがあります。
美味しそうなものを目の前にした時に使う「舌なめずりをする」という表現も似た様な感じですね。
不満がある、不機嫌な時に使う場合の舌つづみの類語には「舌打ちをする」があります。
舌つづみと言えば、舌打ちをするなど不機嫌な時に使う意味としてはあまり知られていないので合わせて覚えておくようにして使い分けが出来るようにしたいですね。
まとめ
今回の記事はいかがでしたか?
舌つづみの意味や正しい使い方、類語や語源などについてご紹介しました。
一般的によく使われている言葉、認知されている言葉でもよく調べてみるとまた別の意味があったりしますよね(´ω`)
舌つづみと舌づつみは一体どちらが正しいのかよくわからないという人も多いかと。
本来の舌つづみが舌づつみになぜ誤用されるようになったのかというと、昔の流行が絡んでいるとも言われています。
江戸時代には逆さ言葉が流行った時期があり、正しい言葉を入れ替えたり逆さまにして言うのが流行っていた時期があります。
今でいう業界用語的な感じで、意味が周りに伝わる範囲内で行われていた言葉遊びの一つといった感じでしょうか💡
そんな時代背景もあり、音位転倒が起きて音が入れ替わり新しい言葉が作られたそうです。
舌つづみの他には「新しい」、あらたしいだったのがあたらしいに変わり、「しだらない」がだらしないに変わったと言われています。
以上、参考になれば幸いです✨

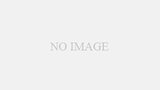
コメント