
料理には様々なネーミングのものがありますが、和食の場合は日本らしい名前がついているものが多いです(‘ω’)ノ
松風焼きと言っても、由来は名前からは連想しにくいですね。
松風焼き(まつかぜやき)とは和菓子の松風のような見た目をした料理のことで、おせちにもよく使われています💡
松風(まつかぜ)と呼ばれたり、鳥肉が使われている場合には鳥松風(とりまつかぜ)などと呼ばれることも。
作り方はとっても簡単で、一度にたくさん作っておくことも可能なのでおかずとして使ったりおつまみに使われています✨
今回は、
・松風焼きの意味や由来
・簡単な作り方
などについてご紹介したいと思います。
松風焼きの意味とは

松風焼きは和菓子の松風のような見た目をしていると言われていて、味噌松風と呼ばれ京都の名物焼き菓子の一つとなっています💡
小麦粉に砂糖や卵を加えて、それを水で割り更に味噌を付け足してそれからよく発酵させたお菓子で、見た目は厚焼き玉子のようなカステラのような非常に食べ応えがある焼き菓子。
料理でいう松風焼きは、ひき肉やすり身の肉に調味料や卵などを混ぜて表面には青のりやゴマなどをまぶして焼いたもののことです(‘ω’)ノ
本来は、仕上げとしてけしの実を表面にまぶして焼いて出来上がりになるのですがけしの実よりも手に入れやすい白ゴマが使われることが多いんですよね。
肉に鶏を使ったものは鶏松風や鳥松風などとも呼ばれたりします。
必ず肉ではないといけないわけでなく、魚のすり身が代わりに使われることもあるなど幅広いバリーションがある食べ物なんです。
縁起の良い食べ物でもある!
おせちには、
・黒豆
・紅白のかまぼこ
・栗きんとん
・エビ
など色々な食材が少しずつ盛り込まれていて、それぞれに健康長寿だったり金運だったり、子だくさんだったりと縁起に良い意味が込められています。
関連:おせち料理を食べるようになった由来は?具材の意味もまとめてみた
松風焼きは、表面にだけけしの実がパラパラとまぶしてあるので裏には何もない状態になりますよね❓
その姿から、裏には何もない、隠し事のない正直な生き方が出来るようにという意味があると言われています。
次のページでは、松風焼きの切ない由来についてご紹介したいと思います。

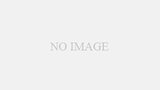
コメント