
クチナシとは、アカネ科の植物で通常植物は実が熟すと割れたり破裂したりすることが多いですが、熟しても割れないため「口が無い」という意味からクチナシと呼ばれるようになったそう💡
一般的には園芸用として栽培されることの多いクチナシですが、実は山梔子(さんしし)と呼ばれる漢方薬の原料になったり、着色料として使われるなど様々な使い方がされています。
クチナシの果実から作り出される色素は天然のものになり、食品添加物としてお菓子やガム、シロップ、アイス、サプリメントなど様々な食品にも(‘ω’)ノ
そのため、身近な存在となっていますがアレルギー体質の人は特に安全性には十分注意したほうが良いでしょう。
今回は、
・クチナシ色素の表示方法や安全性、食紅との違い
・主な使い方
などについてご紹介したいと思います。
クチナシ色素の表示例

クチナシの色素は、古くから使われてきた色素でありおせちの栗きんとんなどより色を鮮やかに出すために家庭でも昔から料理に使われてきたもの✨
その他にも、衣類の染物にも使われるなど日常で欠かせない色素の一つだったとか。
クチナシに含まれる「クロセチン」、「クロシン」と呼ばれるカロテノイド系の色素は黄色、赤、青の三色を作り出すことが可能。
市販されている全ての食品には、使われている成分が細かく記載されているラベルがありますがそこに表示されるクチナシは黄色と赤、青によって名称が少し異なります。
◎黄色系色素
・カロテノイドまたはカロチノイド
・カロテノイド色素またはカロチノイド色素
・クロシン
・クチナシ
・クチナシ黄色素
◎青、または赤系色素
・クチナシ
・クチナシ色素
これらの表記があれば、クチナシ色素を使っているということですね‼
基本的には、食用として使って問題ないのですがもともとアレルギー体質の人は念のため気を付けたほうが良いでしょう。
次のページでは、安全性・食紅との違いについてご紹介します。

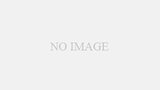
コメント