
年明けの2月から3月にかけて行われる確定申告と言えば、自営業の人が税金の申告をするというイメージがありますがそれだけでなく医療費控除も申告が可能。
医療費控除に関しては申告しなくても別にダメということは無いですが、申告すれば自分が払いすぎた医療費の一部が戻ってきたりします。
なので、余分に払いすぎたお金を還付という形で取り戻すことが出来るので年末になったらその日一年で払い過ぎた医療費がないかどうか確認しましょう。
今回は、
・医療費控除の確定申告の期間
・対象となる条件
・年末調整後に出来るのか?
などについてご紹介します。
医療費控除の対象となる条件とは

体の調子が悪い時って、なぜか立て続けにあちこち不調が出てきて色々な病院に足を運ぶ羽目になったりしませんか?
最初に治療していた疾患が良くなったと思ったらまた別の病気にかかったり、怪我をしたり災難は続くことが多いですよね。
最近病院ばっかり行ってるなという時や、今年はけっこう病院に通ったなと思ったらもしかすると医療費控除が可能かもしれないので支払った医療費を確認しましょう。
医療費控除は一定の条件を満たせば対象となりますが、まずは納税者が自分や生計を共にする配偶者、またはその他親族の為に支払った医療費であることです。
なので、家族が居れば単身赴任をしているお父さんも大学進学のために上京した子供も生計を共にするので家族それぞれにかかった医療費を合算することになります。
そして、医療費の対象となる金額は上限が200万円までとなっています。
計算の仕方
実際に医療機関で支払った合計金額から保険で補てんされる金額を引いた金額、更にそこから10万円(ただし、総所得金額が200万円未満になる場合は総所得金額の5%の金額)を引いた額になります。
つまり、例えば病院で支払った医療費の合計金額がその年の1月1日から12月31日までの一年間の間で40万円になったとします。
そこから、保険金などを差し引いて10万円以下になったら医療費控除の対象にはならないということです。
逆に、一年間で18万円位医療費がかかって保険金の補てんがない場合はそこから10万円を引くと8万円残ることになります。
この残った8万円が医療費控除の金額なのですが、実はこれ全てが戻って来るわけではありません。
所得税の税率をかける
この8万円という金額に、所得税の税率をかけたものが実際に受け取れる金額になっています。
もし、課税所得が300万円だった場合所得税の税率が10%になるので8万円×10%で8000円戻ってきます。
もし、課税所得が2000万円あれば所得税の税率は40%になるので、8万円×40%で32000円戻って来るというわけです。
税金を多く支払っている人の方が、控除額が同じだとしても税金が少ない人よりも必然的に還付金も多くなります。
保険金で補てんされる金額というのは、
・「入院費」
・健康保険などで支払われる「家族療養費」
・「高額の療養費」
・「育児金」
などがこれに当てはまります。
保険金で補てんされる金額は給付目的となった医療費の金額が限度になるので、もし差し引けない金額があったとしてもその他の別の医療費から代わりに差し引かれるということはありません。
医療費控除の対象となるものとして主に以下のものがあります。医師の処方があるか、治療の目的かというところがポイントです。
ー医師の処方がある、治療目的になるもの
・治療費や薬代
・入院時の費用
・定期検診と検査費用
・病院への交通費
・介護保険を使った時の介護費用
対象にならないものとして主に以下のものがあります。治療の目的ではないもの、医師の処方がないものなどです。
ー医師の処方がない、治療目的ではない
✖美容整形費用
✖病気が発見されなかった健康診断費用
✖病院までの自家用車でかかったガソリン代
✖予防接種費用
少し厄介なのですが、一見対象ではなさそうなものでも対象となる場合もあります。
例えば、歯並びの改善などは子供の成長に悪影響を与えるなどといった理由で治療が必要な場合には対象となりますが美容目的で歯列矯正する場合は対象になりません。
マッサージなども、一見対象にならなそうですがそれも治療目的であれば対象となる場合もあります。
あとは、全ての医療費がどれくらいになるのかを計算したら、そこから保険金などを差し引いた金額が10万円以上になれば還付してもらえるということになります。
次のページでは、医療費控除の手続きと年末調整についてご紹介します。

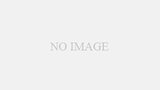
コメント