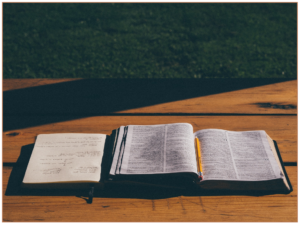
日常の会話の中でもよく使われる「折り紙つき」という言葉💡
何らかの優れた面を持っている人に対して使われたりする言葉ですが、なぜ折り紙が含まれるんでしょうか(・・?
似た様な表現として、「お墨付き」や「札付き」などといったものもありますがそれらとの違いは一体なんなんでしょうか。
そこで、今回は
・折り紙つきの意味や由来
・使い方
などについてご紹介したいと思います(‘ω’)ノ
折り紙つきの意味について
折り紙つきと言えば、色紙で色々な形を作る折り紙が思いつきますが、実はその折り紙はこの表現には関係ありません。
折り紙つきというのは、
・品質が確かなものであると保証されていること
・世間一般で定評を得ていること
などを意味します💡
鑑定保証書がついていることや、その物を指して言うこともありますね(‘ω’)ノ
例えばですが、石の付いた指輪があってそれは本物の宝石ですよと言われても鑑定証があるのとないのとでは買い手にとっても説得力は違いますよね❓
折り紙付きというのは、能力だったり品質などを間違いなく保証できるような時に使うことが多いですね。
札付きやお墨付きはまたちょっと違う
普通は良い意味でしか使われず、悪い意味で定評がある場合は札つきとして、折り紙ではなく札を使うのが一般的。
日常会話ではあまり使わないかもしれませんが、「あいつは札付きのは悪だ」と言っているのをよくドラマで昔やっていたのを覚えています(´ω`)
ちなみに、「お墨付き」という表現も折り紙付きと似た様な意味になるのですがどちらかというと権威のあるところ、権力者などの承認を得るといった感じ。
折り紙付きは、品質に間違いないものや高い能力などを指していうような感じですね。
次のページでは、この表現が使われるようになったきっかけ、由来・語源についてもご紹介します。

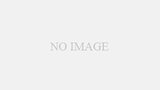
コメント