
お正月期間は縁担ぎのためにもお餅を食べる機会は多いと思いますし、むしろお正月ぐらいしか食べない人も多いのではないでしょうか❓
そのまま焼いて食べたり、お雑煮に入れたり、お汁粉としてスイーツのような感覚で食べることもあると思います(*´ω`*)
一見似ているようですが、お汁粉とぜんざいの違いは一体何なんでしょうか。
今回は、
・お汁粉とぜんざいの違い
・気になるカロリー
・ダイエット中の人でもおすすめのお餅の代替レシピ
などについてご紹介していきたいと思います。
お汁粉とぜんざいの違い
お汁粉とぜんざいに共通する特徴としては、餅と小豆を使ったスイーツであること💡
汁気があるかないか、使っているあんこが粒あんかこしあんかによってお汁粉なのかぜんざいなのかが分かれます👇
●関東
関東では、汁気のある小豆の中にお餅が入っていればそれはお汁粉と呼びます。
使っているあんこが、こしあんでも粒あんでも汁気のあるあんこに餅が入っていればお汁粉なのです。
汁気がなく、お餅にあんをかけたものがぜんざい。
ぜんざいには白玉を添えたり、トッピングして夏のデザートとしてよく食べられます。
●関西
関西では、汁気があるものでもこしあんを使っているものはお汁粉。
粒あんを使っているものは、ぜんざいと言います。
汁気がなくて、餅にただあんをかけただけのスイーツは関東ではぜんざいになりますが関西では亀山と呼ぶことが多いです。
なので、関東と関西ではお汁粉とぜんざいの定義が微妙に違ってきます。
~~~
どこでどんな形で呼び名が変わってしまったのかはわかっていないようですが、一説によるとお汁粉やぜんざいは関西から関東に伝わる時にそれぞれの別のスイーツとして認識されずに広まってしまったと言われています💦
そのため、本来関西では汁気のあるこしあんをつかったスイーツ→お汁粉、汁気のある粒あんを使ったスイーツ→ぜんざい、なのが関東では汁のあるあんこのスイーツは全部お汁粉となってしまったようです(;’∀’)
その他の地域では中に入れる餅の形が違ったり、具材もまた別のものだったり…
と、また違いがあったりするのですがざっくり大きく分けると関東と関西の二種類に分けられるようですね。
甘い小豆に炭水化物のお餅が入れば、食べやすくておいしいのですがカロリーも気になるところです。
次のページでは、気になるカロリーについてもご紹介します。

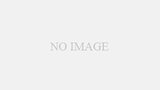
コメント