
どんど焼きとは1月15日に当たる小正月の行事のことで、日本全国で行われる火祭りのことを言います💡
毎年神社などで行われますが、その意味にはどんな意味があるんでしょうか?
また、いつからいつまでの時期に行われるもので、その時に食べられるお団子はどうやって作るんでしょうか?(‘ω’)ノ
そんな疑問をまとめてみることにしました✨
今回は、
・どんど焼きの意味
・いつからいつまでの時期に行うのか
・どんど焼きで焼くお団子の作り方
についてご紹介したいと思います。
どんど焼きの意味は無病息災のご利益
どんど焼きは、お正月期間の飾りとして使っていたしめ縄や松飾りなどを家から持ち寄って神社に返納するという形で積み上げて一気に燃やす行事。
そうすることで、新年もまた一年大きな病気をすることもなく、無事健康で居られるように無病息災のご利益があるそうです(´ω`)
もともとは、年末に各家を周って福を運んでくれる年神様をお見送りするための行事として行われていたものですが、今は健康祈願として参加する人が多いです。
どこの神社でもやっていることなので、自宅から一番近い近所の神社に飾りを持って行ってどんど焼きに参加するのが一般的💡
お札やお守りもOK
お正月の飾り以外にも、お札やお守りなんかも一つの処分方法として一年を過ぎたらどんど焼きに出してしまうほうが良いと言われています。
お守りは、自分で買うこともあると思いますがもらうことも多いかと。
例えば厄年だったから厄除けのお守りをもらったり、安産祈願のお守りをもらったり…人からもらって持っていたお守りがあるはず。
本来であれば、買った神社にお返しするのが一番良いのですが距離的な問題でなかなか気軽に行けないこともありますし、もらったものならどこの神社のものかわからない場合もありますよね(^^;)
郵送で取り扱っている神社もありますが、取り扱っていない神社もあるので処分方法に困ってしまいます💦
お守りは、一生ご利益があるものではなく基本的にその年一年ご利益があるもの。
その年が過ぎたら、お礼に神社に返すかどんど焼きで処分するのが一番良いと言われています。
次のページでは、どんど焼きをやる時期はいつからいつまでなのかについてご紹介します。

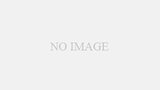
コメント