
道路や住宅街の塀周辺などでよく見かけるカタツムリ。
「マイマイ」「デンデンムシ」などといった様々な呼び方がありますね。
子供の頃に家で飼っていたという人も多いのではないでしょうか❓
雨の日や梅雨の時期に出没が多くなるので、天気が悪い日が続くと家の近くでカタツムリがふと見つかったりするんですよね。
飼育しやすいので、子供が連れてきたカタツムリを自宅で飼うという機会もあると思います★
そこで、今回は
・カタツムリの基本的な飼い方
・主な種類
・気をつけたい寄生虫
などについてご紹介したいと思います。
カタツムリの基本的な飼い方

●飼育する場所
通気性があり、蓋ができるビンや虫かごなどの中が◎
植木鉢の中に土を入れると産卵場所として使えるので、飼育する容器は小さめの植木鉢が入るくらいの大きさにしましょう。
土は、あれば川砂を先に入れその後腐葉土を入れます。
腐葉土はホームセンターなどで売っています。
●湿度があるところが大好き
カタツムリは湿度があるところを好むので、水が溜まらないくらいに霧吹きをかけましょう。
葉の間に入るのが好きなので、落ち葉や小枝なども少し入れておくと良いですよ。
飼育容器は風通しの良い日陰に置き、土は時々太陽に当てて消毒するとばっちりですね。
●実は水は苦手?
カタツムリは、湿気は好きなのですが実は水は苦手💦
雨の日にカタツムリがよく見られるのは、雨が好きで自然と行動範囲を広げているというわけではなく地面に溜まった水から逃げる為に避難するからなんだそう。
そして、その避難中に人間にうっかり見つかってしまうといった感じのようです。
なので、飼育容器の中で水が溜まらないように気をつけましょう。
●餌やり
エサやりに関しては、
・キャベツ
・白菜
・レタス
・キュウリ
・芋
など、野菜なら大概何でも食べますが、野菜だけでは栄養不足になってしまうので卵の殻や貝などもバランス良く与えるようにしましょう。
なるべく小さく切ったり、砕いてあげるようにすると食べやすいはず(‘ω’)ノ
また、カタツムリは雌と雄の区別は無いので土のある飼育容器の中に同じくらいのカタツムリを数匹放しておくだけで大丈夫です。
5月から8月くらいの間に土の中に卵を産み、3・4週間ほどで孵化して赤ちゃんカタツムリが徐々に見られるようになります‼
●夏と冬の過ごし方
小さい時は特に乾燥に弱いので、いつも湿った環境が作れるように配慮しましょう。
赤ちゃんには、餌はやわらかい葉を細かくして与えるようにしましょう。
冬を越させるには、凍結しないよう5度以下にならない場所で寒暖の差があまり無いところで葉や土を多めに入れます。
冬でも霧吹きは忘れないようにしたいですね★
冬眠すると殻に膜が張ったようにになり、そこから出てこなくなりますが3月くらいになり暖かくなってくると自然と殻から出てくるようになります。
一年を通じてあまり寒暖の差がなく、冬でも20度前後を保てると冬眠しないこともあります。
●寿命の目安
カタツムリは大きい種類のもので1年以上、3年から4年ほども生きるものもありますが、一般的には1年くらいかそれ以下の数か月といった寿命となっています。
出来るだけ、乾燥させないように気をつけて飼育することで長生きさせることが出来ますよ。
カタツムリにはどんな種類がある?

カタツムリには様々な種類があって、その数は700~800程にまで及ぶと言われています。
沢山の数があるので見分けるのは大変ですがその中でも代表的なものは、
・北海道に広く生息している「エゾマイマイ」
・本州を中心に生息している「ヒダリマキマイマイ」
・関東を中心に生息している「ミスジマイマイ」
・沖縄などの温暖なところに生息している「タメトモマイマイ」
などがあります。
その他には、
・日本で良く見られる「ウスカワマイマイ」
・国産種である「ニッポンマイマイ」
・外来種である「オナジマイマイ」
等の種類があり全国的に生息しています💡
●見分け方
カタツムリの種類を見分けるにはいくつか方法がありますが、「殻の大きさ」と「巻く向き」、「柄や色」などで見分けがつきます。
1センチ以下の小さなものは子供の場合が多く、成長途中ということもあり柄なども大差がなくどれも似たような見た目をしていることもあり見分けるのは難しいようです。
〇殻の大きさが2センチ以上の場合
左巻き・・・ヒダリマキマイマイ
右巻き・・・ミスジマイマイ、エゾマイマイ、タメトモマイマイ
〇殻の大きさが1センチから2センチくらいの場合
左巻き・・・ヒダリマキマイマイの子供
右巻き・・・ミスジマイマイの子供、ニッポンマイマイ、ウスカワマイマイ、オナジマイマイ
〇柄や殻の形
殻は高さがありてっぺんがとんがっている・・・ニッポンマイマイ(薄茶、こげ茶、黒っぽいのもいる)
殻がまん丸で筋がほとんど入っておらず柄はまばら・・・ウスカワマイマイ(薄茶)、タメトモマイマイ(薄茶に濃い茶色の線が1・2本)、エゾマイマイ(濃いきなり、こげ茶色)
殻が平べったくて巻き数が多く巻き始めは黒か茶色・・・オナジマイマイ
殻がまん丸で筋が数本入っている・・・ミスジマイマイ(薄茶にこげ茶の線)
*****
一般的には、右巻きのほうがほとんどで左巻きのカタツムリはほとんど居ないそうです💧
右巻きと言うのは右手を握った時に出来る渦の形のこと。
左巻きは、左手を握った時に出来る渦の形と覚えておくと分かりやすいですね。
気をつけたい寄生虫について

カタツムリにも種類によっては寄生虫がつくことがあり、人間に寄生すると健康被害を受けるリスクがあるんです。
なので、たかがカタツムリとは思わずに気をつける必要があります(;’∀’)
カタツムリに寄生しやすい虫には、「広東住血線虫」というものがあり感染は沖縄のみと限られてはいます。
でも、人間に寄生すると中枢神経を通って脳に侵入するので脳脊髄膜炎など重い症状を引き起こす可能性があります。
他には、カタツムリの触角、角の部分に寄生する虫で「ロイコクロリディウム」という虫が存在します。
この虫は、本来は鳥に寄生しますがカタツムリがうっかり食べてしまうこともあり体内に寄生します。
人間に寄生した例は日本では無いようですが、接触しないにこしたことはありませんよね。
子供であればカタツムリはつい触ってしまうものですが…どんな寄生虫や菌を持っているのかは分からないのでなるべく素手では触らないようにしたほうが安心です。
もしもうっかり触ってしまった場合は、すぐに石鹸でよく手洗いをするのが一番ですよ。
まとめ
今回の記事はいかがでしたか?
・カタツムリの基本的な飼い方
・主な種類
・気をつけたい寄生虫
などについてご紹介しました。
昆虫でも熱帯魚なんかでも、小動物なんかでもそうですが、何かを飼うというのは家族みんなで一緒に成長を見るのが楽しいですよね。
何より、新しい家族が増えたみたいな感じがして嬉しい気持ちもするものです。
カタツムリは特に育てやすいので、子供が学校帰りに連れてくることもありますよね❓
私も子供の頃、幼稚園から小学校低学年くらいまではカタツムリを連れて帰っては育てていたことがあります。
全ての生き物に言えることですが、カタツムリも人間に害のある寄生虫や菌を持っていることもあります。
素手で触ったら絶対何かに感染するというわけでは無いですが、触った後は必ず石鹸を使って手洗いをするようにしましょう。
手洗いをしっかりしておくことで、未然に病気を防ぐことが出来るはずです‼

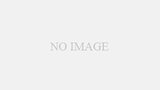
コメント