
温度を表す単位として、「摂氏」「華氏」がありますが世界的に使われているのが摂氏になりますね。
日本でも摂氏で表示されていますよね。
アメリカやジャマイカ、イギリスなどといった一部の国と地域では未だに「華氏」が使われています。
海外旅行などで訪れた際に、今摂氏では一体何度なのかわからなくなってしまった人は多いのではないでしょうか。
華氏を変換すれば摂氏にすることも出来ますが、普段摂氏で慣れてると簡単なことではないですよね。
また、摂氏と華氏の違いや由来についても意外と知られていないので今回まとめてみることにしました。
摂氏とは?華氏との違い
●摂氏
凝固点(水が固まる時の温度)・・・0度
沸点(水が沸騰する時の温度)・・・100度
この凝固点、沸点をもとに100等分した目盛が摂氏です。
単位はおなじみの「℃」ですよね。
●華氏
凝固点(水が固まる時の温度)・・・32度
沸点(水が沸騰する時の温度)・・・212度
180度の差を100で割ったものが1度なので、摂氏1度上がると華氏は1.8上がります。
単位はあまり馴染みのない「F」となります。
摂氏に関しては、とてもシンプルだと思うのですが華氏に関してはちょっとややこしい印象です。
なぜこのような華氏が出来たのかというと、諸説あります。
・塩と氷を混ぜて作った寒剤という混合物が0度、血液の温度96度を元にして作った
・この温度目盛りを作った人物が当時住んでいたベルリンの当時の最低気温を0度、体温を100度を元にして作った
・当時のベルリンの最低気温と最高気温を元にして作った
など色々言われていますが、詳しくははっきりとわかっていないと言われています。
また、華氏のほうは当時測定が正確ではなかったので後で修正されて今の形になったとも言われています。
次のページでは、摂氏と華氏のネーミングの由来についてご紹介します。

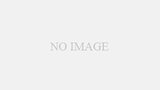
コメント