
桜餅とは、和菓子の一つですが日本の象徴でもある「桜」にちなんだお菓子のことです🌸
淡い桜の花びらを連想させるようなピンク色の餅を、塩漬けした桜の葉で包んだ和菓子。
もとは京都で生まれてその後当時の東京である江戸に伝わったと言われていて、現在では関東風の桜餅と関西風のものに分けられていますがその違いは一体何なんでしょうか❓
今回は、
・桜餅の関東風と関西風の違い
・葉っぱを付ける理由やその種類
などについてご紹介したいと思います。
桜餅の関東風と関西風の違い

桜餅には現在2種類あって、主に関東風と関西風に分けられます💡
関東風と言うのは、薄く焼いた生地で餡を包んだものを葉で巻いたクレープ状のお餅のこと。
別名長命寺、長命寺餅と呼ばれ関東地域では一般的にこちらが主流になりますね(^^♪
長命寺というのは桜餅の名前の由来となっている場所で、東京は隅田川沿いにあるお寺のことです。
そこの門番の一人が、桜の時期には毎日大量に落ちてくる落ち葉の掃除にいつも苦労していたそう…
そこで、ある時ふと考え付いた末に桜の葉を使った和菓子である桜餅を思いついたというのが関東での桜餅の始まりと考えられています✨
関西風の桜餅はまた違う!
一方、関西風というのはもち米を蒸して乾かした後に粗びきにした生地で餡を包み、それを更に桜の葉で巻いたもののことです。
薄っすらピンクの一般的なお餅のような見た目で、道明寺または道明寺餅と呼ばれこちらは関西地域で主流となっている桜餅💡
道明寺というのは、大阪にある道明寺で作られるようになった「道明寺粉」を使っていることからそう呼ばれるようになったそうです(´ω`)
~~~
両者の違いは、関東風はクレープっぽいお餅、関西風はもっちりした一般的なお餅。
関東や関西以外のその他の地域では、全国的には元祖桜餅と言われる関西風の道明寺餅の方が一般的なような気がします。
桜餅には、お餅を包むように葉っぱが添えられていますがその理由は一体何なんでしょうか❓
次のページでは、お餅を包むのに桜の葉を使う理由についてご紹介します。

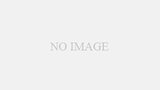
コメント